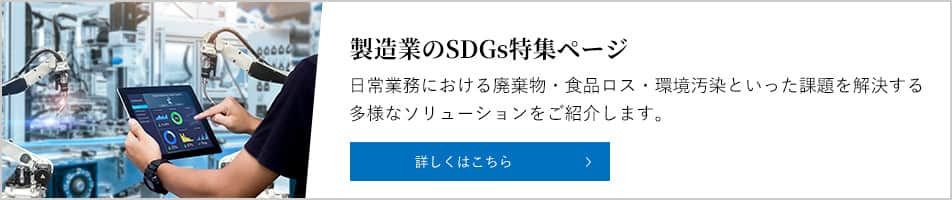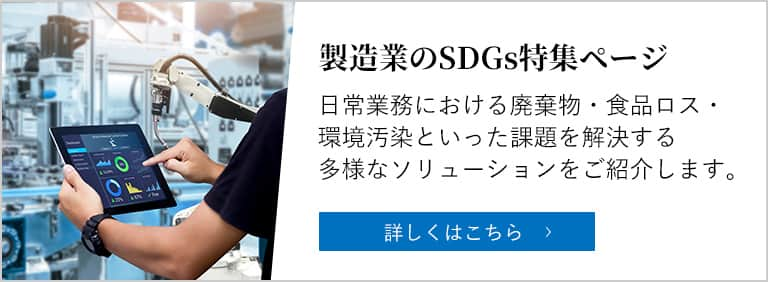日本の繊維産地から考える、持続可能なファッション産業

- 株式会社糸編 代表取締役宮浦 晋哉氏(みやうら しんや)
ファッションキュレーター。株式会社糸編 代表取締役。国際ファッション専門職大学講師。杉野服飾大学服飾学部卒業。学士(服飾)。London College of Fashion Fashion Media and Communication修了。2013年に東京・月島でコミュニティスペース「セコリ荘」を開設し、全国の繊維産地を巡りながらその魅力を発信してきた。2016年名古屋芸術大学特別客員教授のほか多数の大学・専門学校講師として教鞭を執る。2017年に株式会社糸編を設立し、繊維産業・テキスタイルを体系的に学ぶ「産地の学校」や情報発信のプラットフォーム「TEXTILE JAPAN」を運営している。2024年10月からは、産地の余剰在庫を買い取り、販売する活動も開始。年間200以上の工場を訪問し、繊維・アパレル産業の発展に貢献する。主な著書に『Secori Book』(2013年)、『FASHION∞TEXTILE』(2017年)がある。
日本の繊維製品の輸出高は世界的に高く、有名ラグジュアリーブランドにも高く評価されている日本のテキスタイルです。しかし、その繊維産業が今、危機を迎えているとファッションキュレーターとして活動する、株式会社糸編代表の宮浦氏は言います。
繊維産業の現場で何が起きているのか、ファッション産業が持続可能となるには何が必要なのかについて宮浦氏にお話をお伺いしました。
目次
ファッションキュレーターとは
「キュレーター」とは、一般的に博物館や美術館の学芸員のことをいいます。学芸員が世の中にある芸術の価値を発掘して、世間に広く伝えているように、私はファッション業界で同じような役割をめざしたいと思い、創業時の2012年にこうした肩書を使い始めました。
具体的には、デザイナーの支援や繊維産地での素材開発、ブランディングのサポートなどをしています。最近では、行政の事業に関する仕事も行っています。各自治体ではファッション・繊維産業の振興に取り組んでいて、東京都や経産省では若手デザイナーの育成・支援にも熱心です。
 取材風景(写真提供:ファッションキュレーター 宮浦氏)
取材風景(写真提供:ファッションキュレーター 宮浦氏)現在、海外では多くの日本人デザイナーが活躍していて、日本のテキスタイルや繊維も高い評価を得ています。そうした中で、日本のクリエイティブをより良く、持続可能なかたちで広げるサポートを行うのが、私の役割だと思っています。
ファッションキュレーターとなったきっかけは、日本の繊維産業との出合いです。
ファッションの勉強でロンドンに留学中、日本のテキスタイルが、非常に高い評価を受けていることを知りました。
日本の繊維産業に興味をもち始めたとき、東京都の八王子にある織物製造会社が、廃業するというニュースを知ったのです。その会社は、世界に名だたるブランドの素材開発を担う会社で、高い技術があるにも関わらず、廃業してしまうという状況に疑問を持ちました。どうしても話を聞いてみたくなり、その会社に取材を申し込んだことが現在の出発点です。
その後、日本各地の繊維産業を取材し、記事や本にして発信する活動を始めました。そのうちに産地と人をつなぐ場所が欲しくなり、「セコリ荘」というコミュニティスペースを立ち上げたり、繊維産地やテキスタイルについて学べる場所が必要だと「産地の学校」を開講したりと、徐々に活動範囲を広げてきたというところです。
こうした活動を通じて、自然とキュレーターという役割になっていきました。
世界から注目される日本の繊維産地
実は日本の繊維輸出額は世界でも高い水準にあり、多くの国に日本の糸や生地が渡っています。
なかでも、ヨーロッパのラグジュアリーブランドでは、日本のテキスタイルが欠かせません。それは、日本の繊維産地が糸使いや生地の表現、加工技術において、世界中を探してもほかにはない素材を生み出しているからです。
 繊維工場(写真提供:ファッションキュレーター 宮浦氏)
繊維工場(写真提供:ファッションキュレーター 宮浦氏)以前、イタリアのビエラという世界有数の繊維産地から、デザインを学ぶ大学院生数名が研修にやってきました。彼らが驚いていたのは、織物工場での製造の様子です。
日本の織物工場の中には、いまだに「シャトル織機」という機械を用いて生地を織るところがあります。これは古くからある機械で、緯糸(よこいと)を巻き付けた「シャトル(筬・おさ)」が、経糸(たていと)を何度も往復することで生地を織り上げます。
シャトル織機は職人が介在する部分が多く、手間がかかるため、量産には向いていません。そこで、大量生産を行う海外の工場などでは、シャトルを使わない「シャトルレス織機」が主流となっています。
では、なぜ日本には、シャトル織機を使う工場があるのかというと、シャトル織機で織った生地には凹凸がある独特な風合いが生まれるからです。この風合いを表現するために、あえてシャトル織機を使い続けるという工場も少なくありません。そしてそれを求めるデザイナーがどの時代でも世界中にいます。
金属工場とタッグを組んで、古い機械を修理しながら大切に使い続けていることに、海外の学生やデザイナーたちは驚いていました。
ジーンズの「赤耳」で知られるセルヴィッチデニムもこのシャトル織機で織られています。
大量生産の時代になってシャトルレス織機での製造が主流となり、赤耳のデニムは僅少となりました。日本にはこの赤耳付きのデニムを製造する工場が多数あり、高品質で貴重なものとして国内外で人気を集めています。
このように、製造効率よりも質を追い求めた日本の技術が、海外から評価されているのです。
また、取引の安定性も海外企業から信頼されるゆえんです。日本企業は、欠陥のない高品質な製品を、納期通りに納めるという信頼感があります。日本人からすると当たり前のようなことですが、海外企業との取引においてはそこも評価されるポイントとなります。
日本の繊維産地が直面する人材不足問題と取り組み
どの業界も同じだと思いますが、日本の繊維産地も深刻な人材不足となっています。
繊維産業のDX化は業界でも直面している課題ですが、職人としての技術が必要な分野であるだけに、デジタル化して全てが解消されるわけではありません。
新たな人材を確保するためには、いかに多くの人に繊維産地のことを知ってもらい、興味をもってもらうかが重要です。
そこで近年トレンドとなっているのが、オープンファクトリーです。
 繊維工場(写真提供:ファッションキュレーター 宮浦氏)
繊維工場(写真提供:ファッションキュレーター 宮浦氏)火付け役は新潟県の燕三条市で行われた「工場の祭典」だと思います。金属加工で有名な燕三条市で、地域の工場が連携し、数日間工場見学などのイベントを実施したのです。
このイベントの反響が大きく、その後各地でオープンファクトリーイベントが開催されるようになりました。繊維産地でもこの流れがあり、山梨県の「ハタオリマチフェスティバル」や愛知県・岐阜県の「ひつじサミット尾州」などが人気を集めています。
その他にも、山形、兵庫、福井などオープンファクトリーのムーブメントは全国に広がっています。一部手伝わせてもらった経験からいうと、こうしたイベントで重要なのは、地元の企業さん1社1社の協力です。
もともと人前に出るのが不得意な方も多いので、最初は抵抗感もあるでしょう。ですが、オープンファクトリーの様子を見ていると、人付き合いに不慣れな職人さんが真剣に話す言葉に、参加者の方は惹き付けられているようです。
産地一体となったオープンファクトリー開催には、組合や市役所の力はもちろん、地元のリーダーの旗振りは欠かせません。まずは、産地が同じ課題に向き合うという機運を作ることが大事だと思います。
海外からは環境負荷への取り組みも求められる
ファッション業界にとって、環境問題も大きなテーマです。
国内繊維産業でも省エネルギー化や、熱源の再利用、廃棄物のリサイクルやアップサイクルへの意識は、ここ数年で大きく発展しているように感じます。
なかでも、環境負荷に配慮していることを示す認証取得や、トレーサビリティ情報の開示は、海外に輸出する上で不可欠です。
 ※画像はイメージです
※画像はイメージです特にヨーロッパでは上市する製品に厳しい環境規制が設けられており、それらをクリアしなければ輸出が難しいです。国内の繊維会社には売上の半分が海外への輸出という会社も少なくなく、そうした会社にとっては、環境負荷への取り組みは企業存続のために取り組まざるを得ないのです。
さらに、ヨーロッパのラグジュアリーブランドには独自の基準があり、そうしたところに生地を卸すメーカーは、一段も二段も高い環境負荷への対応が求められています。
他方、日本国内はどうかというと、海外ほど環境配慮への規制は厳しくないように思います。ヨーロッパの国レベルで規制するという流れとは異なり、日本の場合は消費者の意識が企業の行動変容につながっていくのかもしれません。
サステナブル生産が次世代ムーブメントに
大学で教える立場として多くの若者に接すると、サステナブルへの意識の高さに驚くことが少なくありません。
生産背景が明確でなければいけないとか、誰かが苦しんで作ったものは買いたくないとか、嘘をつきたくないといった考えが個々の根底にあると感じます。
 ガレージショップ(写真提供:ファッションキュレーター 宮浦氏)
ガレージショップ(写真提供:ファッションキュレーター 宮浦氏)しかし、それは30~40代のデザイナーにも見て取れることです。大企業に勤めていたデザイナーたちは、大量生産され世界中に流通される面白さを経験しながらも、顧客の顔が見える仕事がしたいと独立する方も多いです。そうしたデザイナーたちが、産地を回って、素材や生産背景にこだわったブランドを立ち上げるといったことが増えている印象です。
それは国内外問わず、この年代のデザイナー全体に言えることで、次世代のムーブメントのような気がします。
消費者の意識にも同じようなムーブメントが起きていて、イタリアではヴィンテージショップの人気が高まっていたり、アメリカも二次流通やクラフトマンシップのようなことが見直されたりしています。
作り手は自分たちの手の届く、責任が取れるものづくりを、消費者は価値あるものを大切にしようという意識の変化が、世界的に起こっていると考えています。
ファッション産業の未来のために必要なこと
これからの日本のファッション産業に必要なことは、海外マーケットへの展開です。
日本はよくも悪くも国内マーケットが大きいため、アパレル製品やアパレルブランドの海外進出が進んできませんでした。生地においては世界有数の輸出国であるにも関わらず、その生地を使った最終製品の輸出は少ないのです。
 産地の学校(写真提供:ファッションキュレーター 宮浦氏)
産地の学校(写真提供:ファッションキュレーター 宮浦氏)この最終製品の売上が伸びれば、そこに紐づく繊維産業も仕事が増え、いい循環になります。現在は国内の生地を海外に輸出し、海外の製品を日本で販売するというねじれが起きています。
このねじれを解消し、マーケットを広げることがファッション産業の未来に必要なことでしょう。そのためには、英語力や国際感覚の習得が必要です。
私が教える大学でも、国際感覚を養うために英語教育を強化しています。また、2017年から私が運営する「産地の学校」でも、可視化してきた課題に向き合っていきたいと思っています。こうした活動が、ヨーロッパのスタートアップブランドがそうであるように、国内で製造し、海外で販売するという流れに将来的につながると信じています。
編集後記
華やかできらびやかな世界のファッション産業は、日本の繊維産地が支えているということを、もっと私たちは知るべきだと思いました。その点では、各産地で開催されているオープンファクトリーは、人材不足解消だけでなく、消費者と産地を近づける方法としても有効だと思います。宮浦さんのお話しから、ファッション産業を持続可能なものとするには、私たち消費者の意識や行動も変わらなくてはならないと改めて感じました。

- 堀江恵美子
インタビュー記事の執筆を中心に活動。士業や医師、経営者のほか、インタビュー慣れしていない人物へのインタビューも得意とする。インタビュイーが言語化できていないことを汲み取り、読者に分かりやすく伝えることがポリシー。